納豆のきほん
ネバネバとした食感と独特の香りが好きな人にはたまらない「納豆」。栄養バランスに優れた納豆は、原料である大豆のよさをそのまま受け継ぐだけでなく、納豆菌の働きによってさらにパワーアップしています。納豆菌がつくりだすたくさんの消化酵素や代謝に必要なビタミンB1やB2、骨を丈夫にするビタミンK2、血栓を溶かして血液をサラサラにする納豆ならではの酵素「ナットウキナーゼ」などが含まれた、日本のスーパーフードの代表格ともいえます。
納豆のはじまり

納豆の発祥については諸説あり、誕生の時期についても定かではありません。ひとつには平安時代後期に活躍した源義家の軍勢が、兵糧として稲わらで編んだ俵に詰めて運んでいた煮豆が馬の体温で発酵して納豆になったという説があり、奥州遠征の道沿いの秋田から茨城には納豆発祥の伝説と共に、名産地が多く点在しています。このように昔の納豆は蒸した大豆を稲わらで包み、そこについた天然の納豆菌で発酵させていたため、蒸し大豆とわらの出合いが始まりだと考えられています。
納豆という言葉が初めて文献に登場したのは、室町時代の〈精進魚類物語〉というおとぎ話。〈平家物語〉のパロディで、納豆や野菜などの精進物たちと魚や鳥という生臭物たちが戦うという話のなか、精進物側の大将に納豆が選ばれているのです。その名も〈納豆太郎糸重〉です。
江戸時代には「納豆売り」が毎朝納豆を売り歩き、朝食にご飯、納豆、みそ汁を食べるのが定番化していたといいます。また、みそ汁に納豆を入れる納豆汁も食べ方の主流であり、江戸初期発行のポルトガル語で日本語を解説した〈日葡(にっぽ)辞書〉にはすでに「Natto(納豆)」に加えて「Natto jiru(納豆汁)」も載っています。
どんな製法?
納豆の基本的な材料は大豆と納豆菌のみ。伝統的な製法は、大豆を蒸して冷まし、煮沸消毒した稲わらでつくった「わらづと」に入れて、40℃前後の環境で発酵させます。わらにすみついた天然の納豆菌が瞬く間に繁殖して、22〜24時間ほどで納豆が完成します。
現在はわらの安定供給の難しさなどから天然の納豆菌を使った納豆の生産量は少なく、培養された納豆菌を用いた納豆が一般的。蒸した大豆に納豆菌を散布し、販売用の容器に詰め、温度や湿度を調整した「室(むろ)」と呼ばれる発酵室で16~18時間ほど発酵させます。発酵完了後は冷却して24時間ほど熟成し、発酵を落ち着かせて完成です。
納豆菌が繁殖すると、大豆のたんぱく質や炭水化物が分解されて、納豆特有の香りや味、ネバネバが生まれます。この粘性物質はポリグルタミン酸で、旨み成分の一種であるグルタミン酸が結合したもの。これは昆布の旨み成分と同じもので、納豆のおいしさの秘密といえます。糸を引けば引くほど旨み成分が増します。
どんな種類?
大豆を発酵させてつくる「納豆」は大きく2種類に分類されます。ここまで説明してきた納豆菌で発酵させた「糸引き納豆」と、麹菌で発酵させた糸を引かない「塩辛納豆」です。そして、糸引き納豆は「丸大豆納豆・ひきわり納豆・五斗納豆」の3種類に分類されます。
-
- 丸大豆納豆

- 原料の大豆を丸ごと蒸してつくる最もポピュラーな納豆。使用する大豆の大きさによっても分類されており、「大粒大豆・中粒大豆・小粒大豆・極小粒大豆」がある。さらに、大豆の品種や付属のタレなどもさまざまあり、バリエーションが豊か。豆のふっくらとした食感を楽しむことができる。
-
- ひきわり納豆

- 大豆を炒ってひき、皮を取り除いたあとに納豆菌をつけて発酵させた納豆。青森、秋田、岩手などでは江戸時代以前からつくられていたという。丸大豆納豆と比べて、納豆菌がつく大豆の表面積が大きいため、旨みを強く感じる。また、皮がないので食感がやわらかく、消化しやすい。
-
- 五斗納豆

- ひきわり納豆に米麹と塩を加えて、発酵・熟成させたもの。山形県米沢地方で古くからつくられており、五斗(約90リットル)も入る大樽で仕込んでいたことからその名がついたとか。現在は〈雪割納豆〉として販売されているものが有名。
-
- 塩辛納豆
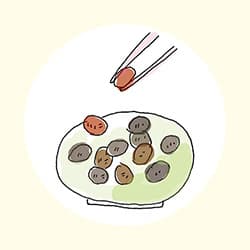
- 納豆菌ではなく麹菌と塩水で発酵させ、乾燥させたもの。黒褐色で塩辛く、風味は溜醤油や八丁味噌のよう。奈良時代に中国から伝わり、お寺でつくられることが多かったことから「寺納豆」とも呼ばれている。
どんな嗜好と産地?
生産量全国1位なのは「水戸納豆」を有する茨城県(〈全国納豆協同組合連合会〉調べ)。茨城県ではもともと農家などで納豆づくりが盛んだったようですが、1889(明治22)年に初代笹沼清左衛門という人物が納豆の商品化をしたのが「水戸納豆」の始まり。ちょうど水戸線開通の年と重なり、駅前やホームで売られると水戸のお土産品として人気を博し、全国にその名を知らしめるようになったといいます。
納豆は、関東、北陸、東北、北海道など関東以北で消費量が高く、西日本ではあまり食べられてきませんでした。もともと雪深い米作地域で、冬場の魚や野菜などに代わるたんぱく源として、納豆は重宝されていました。一方、温暖な気候で瀬戸内海などから容易に魚が手に入った西日本では、納豆をつくる習慣があまりなかったようです。しかし、現在では納豆は低価格で手に入りやすいことと健康機能性が高いことから、全国的に人気となり、市場規模も拡大しています。


納豆のなかまたち
日本のみならず、アジアやアフリカなどの海外にも納豆に似た発酵食品があります。いずれも茹でた大豆に何らかの菌をつけて発酵させたもの。韓国の「チョングッチャン」、タイやラオスの「トゥアナオ」、インドネシアの「テンペ」のほか、日本の塩辛納豆に近い中国の「豆豉(トウチ)」やネパールの「キネマ」、西アフリカの「スンバラ」など、各地に存在しています。
-
- チョングッチャン

- 韓国の大豆発酵食品。茹でた大豆を納豆菌に似た枯草菌の力で発酵させ、発酵後に塩と唐辛子粉などを加えて貯蔵性を高めている。日本の納豆のような糸を引く粘り気と独特の香りがある。チゲをつくるのによく使われる。
-
- トゥアナオ

- タイやラオスで食べられている大豆の発酵食品。茹でた大豆を枯草菌で発酵させたもので、粒状のもの、それをすりつぶしてペースト状にしたものやそれをさらに薄くせんべい状に広げて乾燥させたものがある。もち米と一緒に食べたり、炒め物などに使われたりする。
-
- テンペ

- インドネシアの大豆発酵食品。茹でた大豆をバナナの葉で包み、テンペ菌というクモノスカビの一種で発酵させた、ブロック状のもの。日本の納豆のような粘り気や匂いはなく、主に揚げ物や炒め物などに使われる。ヴィーガン食材として世界的にも注目されている。

-
監修:小泉武夫(こいずみたけお)1943年福島県の酒造家に生まれる。農学博士。東京農業大学名誉教授のほか、全国の大学で客員教授を務める。専攻は醸造学・発酵学・食文化論。食にまつわる著書は140冊以上。国や各地の自治体など、行政機関での食に関するアドバイザーを多数兼任。発酵文化の推進ならびにその技術の普及を通じてさまざまな発展に寄与することを目的とした「発酵文化推進機構」の理事長も務める。 発酵文化推進機構公式サイト






